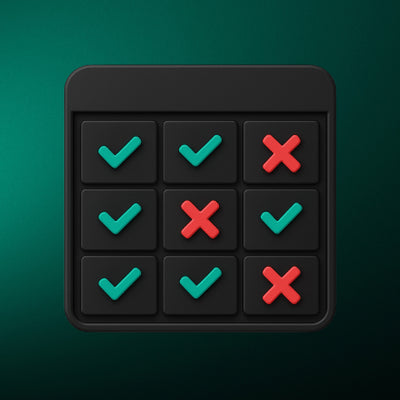ブログ7 min read
ポリリズムを解説 – 知っておきたいポイント!
ポリリズムが何かを学んで、楽器の練習に取り入れたり、音楽の作曲をより豊かにしよう。

ポリリズムの概念は比較的わかりやすいけど、実際に演奏するのは簡単じゃない。この投稿では、ポリリズムが何かを説明するから、ぜひ楽器練習や作曲に取り入れてみて。必要なのは、リズムの細分化やビート、メーターの基本的な理解だけ。さあ、始めよう!
ポリリズムとは?
基本的に、ポリリズムとは同じ基本パルスを基準にした2つ以上の異なるリズムの組み合わせのこと。クロスリズムとよく似ているけど、細分化の仕方が違うんだ。
例えば、4/4拍子があるとしよう。一つのリズムレイヤーはその小節の4拍を基準にして、もう一つは同じ4/4小節を5つに分割する。これが一般的に5対4、または5:4ポリリズムと呼ばれるもの。両方のリズムが同時に演奏されると、全体で一つのリズムフレーズとして感じられる。
とはいえ、普通は演奏されるリズムの一方が非整数のリズム細分化(例えばクインタプレット)に基づいていて、もう一方が2の倍数でパルスを分割していることが多い。必ずしもそうでなくてもよくて、例えば3連符とクインタプレット(3:5)を重ねることもできる。
前にも言ったけど、4:8の細分化はポリリズムとはみなされない。なぜなら、2つの4ができてしまい、同じようにビートを分割するから。この場合は、同じ細分化を使って2つ以上のリズムを重ねるので、クロスリズムと呼ばれる。
ポリリズムの例
さて、説明はこのくらいにして実際に音を聴いてみよう。次のポリリズム例は、3拍と2拍が重なる(3:2)の複合リズムだ。
前述の通り、5:4ポリリズムのように他の細分化を組み合わせることもできるよ。
さらに、5:4:3のように複数のポリリズムを重ねることもできる。
それぞれが独特のリズム感を生み出すから、好きなものを選んでみて。ドラムやパーカッションパート、またはメロディック/ハーモニックな楽器にも応用できるよ。
パーカッションでの4:3ポリリズムの例。メインメロディーとコード進行はクインタプレット(5連符)の細分化に基づいていて、全体として5:4:3のポリリズムになっている。.
ポリリズムに取り組むときは、まず全体のリズム感に集中して、そこから構築していこう。その後は、通常のポリリズムの細分化に縛られずに自由に演奏して大丈夫。影響は受けつつも、より自然なリズムのフレージングを楽器全体に広げていこう。
ポリリズムではないもの
とてもシンプルなコンセプトですが、このテーマについて誤解や勘違いを見かけることがあります。そこで、あなたのために、僕が見つけたことをいくつか紹介します。
1. 同時に異なる小節の長さがある場合、それはポリメーターです。例えば、ピアノが3/4拍子で4小節のフレーズを演奏し、ドラムが4/4拍子で3小節演奏してピアノのフレーズと合流する場合などです。
2. シンコペーションは、裏拍にアクセントをつけるテクニックです。ポリリズムは異なるリズムを重ねることでシンコペーションを生み出し、複合リズムがシンコペートして聴こえることがあります。
3. ポリリズムは変拍子ではありません。ポリリズムを使って変拍子で書くこともできますが、4/4や3/4のような一般的な拍子の音楽で聴くことの方が多いです。
4. 時々、クロスリズムという言葉がポリリズムと関連付けられているのを見かけるかもしれません。この場合、2つ以上の補完的なリズムが同時に演奏されるという点で、コンセプトはとても似ています。でも、説明した通り、まったく同じではありません。ポリリズムでは、少なくともひとつのリズム層が異なる拍の分割を使っています。
ポリリズムはどんな楽器にも応用できる?
この言葉はドラマーがよく使うのを耳にしたことがあるかもしれません。でも実は、どんな楽器でもポリリズムを作り出すことができます。例外は、モノフォニック楽器でソロ演奏している場合です。でも、少なくとも2つ以上のモノフォニック楽器が一緒に演奏していれば、ポリリズムを作ることができます。ひとりでソロ演奏しながらポリリズムを奏でられる楽器の例としては、ピアノ、ギター、ドラムなどがあります。
なぜポリリズムは重要なの?
音楽心理学のいくつかの研究では、音楽のリズムが体内のリズム(例えば心拍数の上昇)に影響を与えることが示されています。時間が経つと、体のリズムは外部からの刺激に合わせて調整されます。これは、リズムが私たちのリスニング体験にどれほど重要かを示しており、ポリリズムはさらに新鮮さや斬新さをもたらす方法のひとつです。
ポリリズムは曲に深みや意外性を加え、音楽を通じて感情的な反応を引き起こす要因にもなります。これは音楽心理学でも研究されています。エブ・アンド・フロー理論によると、音楽の特定の特徴によってリスナーの覚醒や感情的な反応が引き起こされることがあります。この特徴は、音楽の続きに対するリスナーの期待を裏切ったり、遅らせたり、あるいは裏付けたりします。この場合、ポリリズムの使用によって起こるのです!
ポリリズムはあらゆる音楽ジャンルで見られます。音楽にワクワク感を加えたり、創造力を刺激したりするからです。ポリリズムの魅力は、シンプルなパターンを使って複雑なリズム構造のように聴こえることです。楽器奏者や作曲家として、ポリリズムを理解し演奏できる力は、どんなジャンルを学ぶ場合でも身につけておきたいスキルです。
ポリリズムの他の使い方
ポリリズムで遊ぶときに作り出せるすごい効果の一つがテンポモジュレーション、つまりメトリックモジュレーションだよ。テンポも、違う調に転調するみたいに変化させることができる。もちろん、曲のセクションでテンポやBPMを上げたり下げたりすることもできるけど、この場合は、実際にはテンポが変わっていなくても、フレーズが遅くなったり速くなったように感じることがあるんだ。まるで錯覚みたいに、新しいテンポに変わったような印象を与える。これが暗示的なメトリックモジュレーションと呼ばれるものだよ。
やり方の一つは、今まで使っていたものと対照的なリズム分割を導入することだよ。リズムパターンのグループの自然な、または予想されるアクセントをずらすことで、メトリックモジュレーションの印象を与えることができる。下の例では、16分音符と8分音符の3連符をアクセントをずらしながら切り替えることで、そのコントラストを感じられるよ。
この例では、8分音符の3連符のアクセントを3つごとではなく4つごとに変えているよ。. ずっと同じ基本リズムをキープしているよ。
でも、言った通り、ポリリズムを演奏することで暗示的なメトリックモジュレーションも実現できるよ。このテクニックは、リスナーの注意を引いたり、バリエーションを加えたり、新しいテンポへのモジュレーションの準備として使うことができるんだ。
この例では、5:4のポリリズムを使ってテンポが速くなっているような印象を出しているよ。キックとスネアは5連符の分割、ハイハットは1拍に4つの音符の分割だ。
まとめ
この記事では、ポリリズムとは何か、そして何ではないかを明確にして、音楽の勉強を妨げる誤解を避けてきたよ。これで、ポリリズムを練習や作曲に取り入れる可能性を感じたり、もっとインスピレーションを得られたんじゃないかな。いろんなポリリズムの組み合わせを使って、予想外のリズムの景色を作ったり、メトリックモジュレーションを暗示したりできるよ。これは、ポリリズムでできることのほんの一部にすぎない。さあ、これからどんどん探求してみて!
著者について:
ペドロ・ムリノ・アルメイダは、音楽プロジェクトFollow No Oneで受賞歴のある作曲家であり、熟練したミュージシャン、そして経験豊富な音楽教師だよ。彼はBeyond Music Theoryというブログを運営していて、初心者から上級者までの音楽学習者や、音楽理論を学びたい人、使い方を知りたい人、作曲や音楽制作のスキルを高めたい人のために、ツールや指導を提供しているんだ。